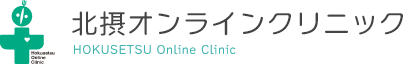やせましょうだけじゃダメ?
― 肥満とスティグマの本当の関係 ―
この記事の目次
はじめに
「やせましょう」
健康診断や病院で、そう指摘された経験がある方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、ただ「やせなさい」と言われても続かない、思うように成果が出ない。
そんな経験を繰り返している方も少なくありません。
その背景には、肥満をめぐる「スティグマ(偏見・差別)」が深く関係しています。
肥満は生活習慣だけでなく、遺伝・環境・心理・社会的要因が複雑に絡み合う“身近な健康課題”です。
単純な「自己責任論」では解決できないのです。
この記事では、肥満とスティグマの関係、そして健康的な減量を実現するための医学的サポートについて詳しく解説します。
日本における肥満の現状

日本では、成人男性の約3人に1人、女性の約5人に1人が肥満(BMI≧25)とされています。
肥満は以下のような病気と深く関わっています。
・糖尿病
・高血圧
・脂肪肝
・睡眠時無呼吸症候群
・心血管疾患
つまり「肥満」は美容上の問題ではなく、命に関わる疾患リスクそのものなのです。
「やせましょう」だけでは変わらない理由
数字だけでは不十分
体重やBMIといった数字は大事ですが、減量成功を左右するのは数字だけではありません。
起床・就寝時間、食習慣、仕事環境、家族関係、ストレス。
生活の背景や心理状態を理解しなければ、長期的な改善は難しいのです。
「自己責任論」の落とし穴
「食べすぎ」「運動不足」「自己管理ができていない」
肥満をめぐる会話には、しばしばこうした“自己責任”の視点が潜んでいます。
しかし実際には、遺伝的体質や生活環境など個人では変えにくい要素も大きく影響しています。「やせろ」という言葉が、本人を追い詰め、かえって改善を妨げることも少なくありません。

肥満スティグマとは、肥満のある人に向けられる偏見や差別のことです。
・医療現場で「ただ痩せればいい」と言われる
・学校や職場でからかわれる
・就職活動で不利になる
こうした経験は、本人に深い心理的ダメージを与えます。
結果として、
・自己肯定感の低下
・ストレスによる過食
・健康サービスや医療の利用回避
といった悪循環を招きます。肥満スティグマは、健康格差を拡大し、支援を受けにくくする大きな障壁となっているのです。
スティグマが減量を妨げる理由
心理的影響
「どうせ自分なんて痩せられない」という諦めにつながり、減量意欲を失わせる。
身体的影響
ストレスホルモン(コルチゾール)の増加で、かえって脂肪がつきやすくなる。
社会的影響
偏見があるために周囲の協力が得られず、孤立した減量になる。
つまり、肥満治療では「スティグマを排除」しなければ効果は上がらないのです。
肥満診療は「数字」だけでなく「背景理解」がカギ
医師が肥満診療を行う際、重要なのは体重・BMIだけに注目しないことです。
・睡眠の質
・食習慣(朝食の有無・夜食の頻度)
・ストレスや心理状態
・職場や家庭の環境
これらを総合的に理解し、生活習慣や心理支援を含めて初めて“持続可能な減量”が実現できます。
日本社会に根強い「やせ至上主義」

日本では、特に女性を中心に「細身であることが美しい」という価値観が根強く存在します。
実際、BMIが標準範囲内であっても「太っている」と感じてダイエットを繰り返す若年層は少なくありません。
・学校でのからかい
・就職活動での見た目偏重
・結婚や恋愛における「やせ信仰」
こうした社会的圧力は、健康的でない無理な減量や摂食障害につながることもあります。
つまり、肥満スティグマは「太っている人」だけでなく、「痩せているのに痩せなきゃと追い込まれる人」にも影響を与えているのです。
国際比較:欧米と日本の違い

欧米では「ボディポジティブ」という考え方が広がり、体型の多様性を尊重する動きが進んでいます。
プラスサイズモデルが活躍し、肥満=不健康という一面的なラベルを貼らない文化が育ちつつあります。
一方日本では、まだまだ「痩せこそ正義」という風潮が強く、肥満スティグマが解消されにくい環境です。 この違いが、肥満治療や減量支援のあり方にも影響を与えています。
心理支援の重要性
肥満治療は「体重を減らすこと」だけではありません。
むしろ、心理的サポートが不可欠です。
・行動療法:食習慣や生活習慣を少しずつ変えるアプローチ
・カウンセリング:自己肯定感を高め、無理のない減量を継続
・集団サポート:同じ課題を持つ人同士の励まし
スティグマによって傷ついた心を癒やし、支えながら進めることが、成功の鍵になります。
医学的アプローチ:メディカルダイエットという選択肢
近年は、生活習慣改善だけでなく「薬物療法」を組み合わせたメディカルダイエットが注目されています。
主な薬の選択肢
・マンジャロ(チルゼパチド)
GLP-1とGIPの作用を併せ持ち、食欲を抑制しつつ血糖値を改善。
糖尿病治療薬として承認済みで、肥満治療にも有効性が報告されています。
・リベルサス(経口GLP-1)
飲み薬タイプで、注射が苦手な方でも続けやすい。
・メトホルミン
糖代謝を改善し、体重増加を抑える効果。特に糖尿病予防の観点でも重要。
これらはあくまで「魔法の薬」ではありません。
生活習慣の改善と組み合わせて使うことで、初めて安全で効果的な減量が実現します。
当院のサポート体制(北摂オンラインクリニック)
北摂オンラインクリニックでは、肥満を「数字だけでなく背景を含めて理解」しながらサポートしています。
・ オンライン診療で全国どこからでも受診可能
・内科専門医が生活習慣・心理的背景を含めてカウンセリング
・必要に応じてメディカルダイエットを提案
・科学的根拠に基づいた安全な治療方針
・「やせたいけど続かない」「健康のために減量したい」方を全面的に支援します
忙しい方でも、自宅から気軽にご相談いただけます。
まとめ

・日本では成人男性3人に1人、女性5人に1人が肥満
・肥満は糖尿病や高血圧など深刻な病気に直結する
・「やせましょう」だけでは続かないのは、生活背景や心理状態も影響するから
・肥満スティグマ(偏見)は改善を妨げ、健康格差を広げる
・医師によるサポートでは、心理・生活・薬物療法を組み合わせることがカギ
・北摂オンラインクリニックは、生活習慣と医学的治療を両輪で支援
やせたいけど続かない…」そんな方へ
北摂オンラインクリニックが、あなたの心と体に寄り添いながら、無理のない減量をサポートします。
「自己責任」ではなく、「医療と伴走」で、あなたの未来を変えてみませんか?