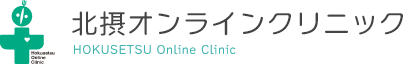お役立ち情報・コラム
GLP-1治療を続けるためのポイント3選|継続できる人の共通点とは?

GLP-1治療を続けるためのポイント3選|継続できる人の共通点とは?
無理のない用量・負担にならない価格・定期フォロー・生活習慣の見直しで“続けやすさ”を設計。

はじめに:なぜ途中でやめてしまう人が多いのか
GLP-1受容体作動薬は注目を集めていますが、「始めたが数か月で中断」という声も少なくありません。主な理由は次の3つです。
GLP-1治療は危険?副作用・安全性を徹底解説|医師監修で安心

◎GLP-1による食欲抑制の仕組み
GLP-1は、食事をすると小腸から分泌されるホルモンです。脳の視床下部にある「満腹中枢」に作用して、少量の食事でも満足感を得やすくする働きがあります。具体的には、GLP-1は血液を通じて脳に信号を送り、食欲を司る神経の活動を抑制します。
これにより、「もう十分食べた」という感覚が早く訪れ、自然に食事量が減ります。
さらに、GLP-1は胃の排出速度を遅らせる作用も持っているため、食後の満腹感が長時間持続します。結果として間食の回数や夜遅くの食欲も減少し、総摂取カロリーの抑制につながります。 (さらに…)
マンジャロ処方が必要な理由とは?処方してもらう方法と注意点を紹介

近年、血糖値の改善とダイエット効果を同時に期待できる薬として注目を集めている「マンジャロ」。もともとは2型糖尿病の治療薬として開発されましたが、その高い食欲抑制作用と体重減少効果から、医療ダイエットとしても利用が広がっています。しかし、マンジャロは誰でも自由に使用できるわけではなく、医師の診察と処方が必要です。本記事では、マンジャロの基本情報や効果、処方を受ける方法、副作用や使用時の注意点まで、これから使用を検討する方に向けて分かりやすく解説します。
マンジャロの効果を徹底解説!血糖値改善と体重管理を同時に叶える理由とは?

近年、糖尿病治療薬として注目を集めている「マンジャロ(Mounjaro)」は、血糖値の管理だけでなく、体重減少効果も期待できる革新的な薬剤です。本記事では、マンジャロの効果やそのメカニズム、最新の臨床データ、実際の使用例について詳しく解説します。